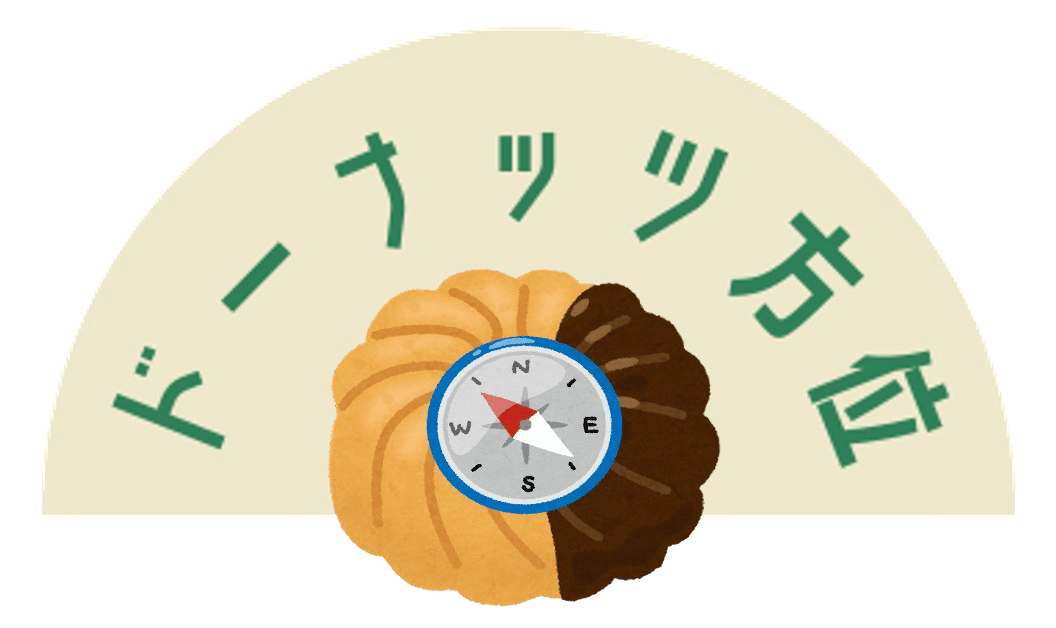僕が今住んでいる町は以前は24時間営業のコンビニが多数ありました。あとは松屋も24時間営業で若い頃は良く深夜まで飲んだ後に松屋で何かを食べたりテイクアウトしたりして帰宅した思い出があります。
さて、現在の町は最寄りのコンビニは1時ー6時まで閉店しております。足を伸ばせばまだ24時間営業のコンビニがあるのでいざと言う時にはまだ問題はありません。
あと松屋の開店がとんでもなく遅くなりました。それでもちゃんと時間通りに開店してくれれば問題ないのですがちょっと開店時間が不定期な感じがしています。
恐らくですがこれらはコロナが影響していると思います。コロナによるダメージで人材確保が難しくなったりしていたり「なんで夜勤バイトする必要あるの?時給低いし」と言う感じなのかも知れません。
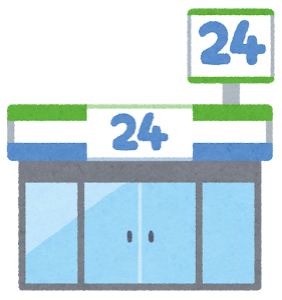
これは生活が不便になったのでしょうか?
僕は『あるべき姿に戻っている』気がしています。
例えば、僕の田舎に初めてセブンイレブンが開店した時(昭和です)、営業時間は名前の通り”7-11時(23時)”だったように記憶しています。それでも随分、生活は便利になりました。当時は個人商店が殆どだったのでまず開店時間は早くても8時位になります。当時、コンビニは割高だけれどもやはり「早朝から深夜まで開いているのは助かる」と言うイメージだったと思います。そもそも”コンビニエンス”って”便利”って意味ですし。
また、上京してからのある日(平成です)、近くにコンビニが無い友人の家に遊んでいった事があります。夜は酒盛りをしていたのですが予想以上に盛り上がってしまいお酒が無くなってしまいました。今ではほとんど無いと思いますが、当時はコンビニは無いけれどタバコとお酒の自販機がけっこうありました。
しかし、自販機と言うと未成年も普通に買えてしまうため自販機でありながら深夜は販売中止していました。僕と友人が絶望したのを覚えています。
その頃は『夜は寝るもの』と言う共通認識がありました。だからこそたまの”夜更かし”は背徳感がありましたし、夜勤の人は大変な仕事だよなと思っていました。
僕は深夜ラジオが好きですし、今は日中にRadikoで聴く事も出来るようになっています。それはそれで便利なのですが、昔は夜更かししないと聴けませんでしたし、だからこそ深夜ラジオは無法地帯のように暴言・失言が蔓延っていても誰も日中に話題にする事はありませんでした。(ちなみにテレビは夜になると放送停止(=砂嵐)していました)
不便を経験しているから便利を実感できると思います。不便を経験していないと、それらは”当たり前”であってサービスなどの質が低下すると”不便”と捉えてしまいます。「いままでが便利すぎた」と感じる事は少ないのではないでしょうか?
ー 例えば、都会生まれの人が『地方移住』したとしましょう。一時期実際にブームになりましたよね。「都会の生活に疲れた。地方に移住してスローライフを送ろう。家賃とかも安いので固定費を抑えられるから多少給与が下がっても問題ない」みたいなヤツです。そして、その地方移住は結構失敗しているみたいです。その理由として「想像以上に不便すぎる」と言うものが挙げられるそうです。例えばまさに”歩いていける距離にコンビニが無い”みたいな感じです。車がないとコンビニに行けないような場所だとお酒を飲んでしまったらもうコンビニへ行けない…と。
僕は北海道生まれですが最初の方に書いたように近くにセブンイレブンがありました。ただ田舎に住む友人の所へ行くと自力でコンビニに行く事はとても難しかった(車がないと無理)覚えがあります。
そのため、地方移住の不便さもある程度予測する事ができます。
不便を当たり前とした時に『便利』を感じられるのは相対的な感覚で当然の事です。でも、不便が当たり前だったから、不便でもいいじゃないか……その不便を楽しみに変えよう!みたいな生き方も現代を生きるための一つのコツなのかもしれませんよ。